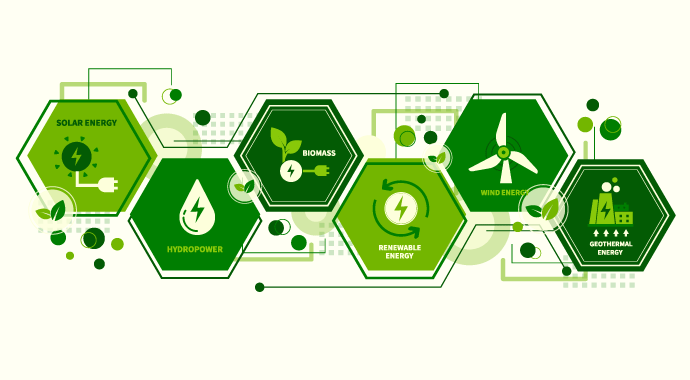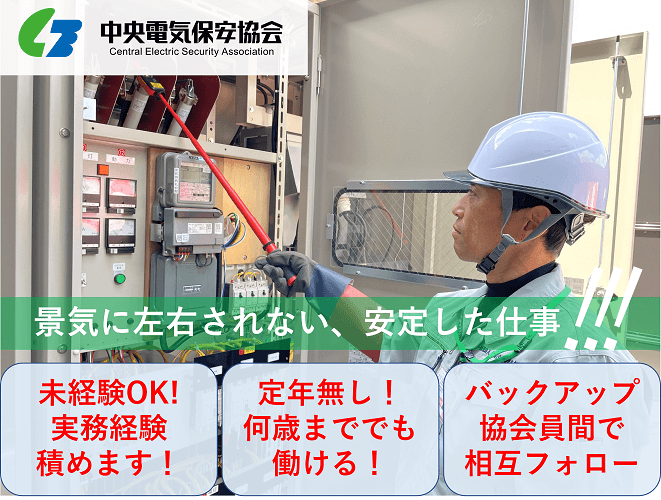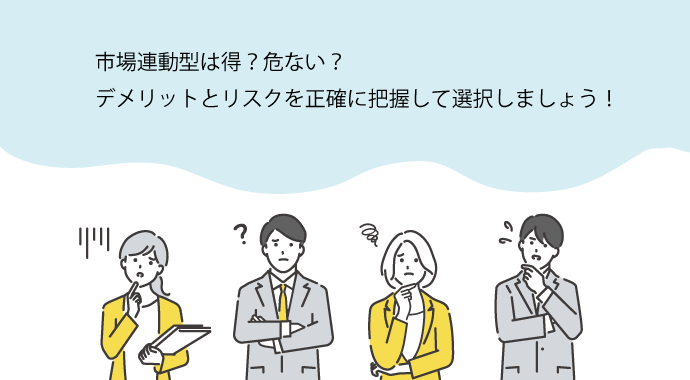今年度の再エネ賦課金が決定しました。3.49円から0.49円(約11%)値上げし、3.98円です。昨年度の2.09円(約149%)値上げに比べるとあまり増えたようには感じませんが、実際のところはどうなのでしょうか?
単価上昇の影響は?
正直なところ、今回の上昇幅では大した影響はありません。毎月10,000kWh使用するとしても、この値上がりでは5,000円にも満たないので、その為だけに何かしらの対策を?と考えると割りに合わないでしょう。
それでも対策が必要な理由
ただ、再エネ賦課金はこれからも上がり続けることが予想されます。何故なら脱炭素社会の実現のため、国が再エネ設備をこれからも増やし続ける方針を取っているからです。
そして、これは単純に再エネ設備を増やさなければいいという問題でもありません。何故なら天然ガスや石油といった地下資源は有限であり、持続可能なエネルギーへの転換を行なわなければ、いずれ燃料が尽き、電気を使用出来なくなるためです。 他の代替手段が新たに見つかることがなければ、いずれ尽きると分かっている燃料を無制限に消費し続けることは出来ません。
電気代の上昇対策を
再エネ賦課金の単価が上がり続けるとしても、それは電気料金を下げることが出来ないということではありません。
経済情勢を考えれば仕方ない、国の方針であれば仕方ない、そう思って電気料金の利用プランを長らく検討していないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
高圧では、電力の小売り自由化が始まったのは2004年です。20年前といえば、CDやDVDが主流になってきて、なんならフロッピーディスクが使用出来る環境がわずかに残っていた時代です。今、仕方ないからとフロッピーを使っている人はいないですよね。
それと同じで、自由化から20年経った今では多くの選択肢が用意されています。
現在は多くの電力会社で市場連動型の電気料金プランを備えており、市場連動型では高騰する時期にだけ固定単価にするハイブリッド型のプランも出ています。これらに影響を受けて、大手電力会社でも2年ほど前から市場連動型のプランを作るなど、顧客のニーズによって状況は変化しています。
これらのプランを検討してみるのも電気代高騰へ備える一つの手段です。
また、当然ですが電気の使用量そのものを減らせば電気代は下がります。
例えば、古い設備は現行のものより省エネ効率が悪いというのは想像に難くありませんが、それらを更新する時には省エネ補助金が利用できることがあります。
そういった「どうせ替えなければならない古い設備」を省エネ効率の高い設備に変更すれば、電気代を下げることが出来るでしょう。そして、その補助金を取るにあたって、加点になる省エネ診断が今は1/10の価格で受けることが出来ます。 こういった補助が出ているうちに省エネを検討するのも一つの手段です。
スターメンテナンスサポートで出来ること
これら電力の切替や省エネ診断、省エネ補助金の取得支援までスターメンテナンスサポートでは請け負っています。 コスト増に困って今すぐにでも負担を減らしたい、補助が出ているならせっかくだから…理由なんて問題ではありません。思い立ったが吉日です。スターメンテナンスサポートでは省エネ省コストのお悩みを抱えている方を助けるため、いつでもお問合せをお待ちしております。
▶お問い合わせはこちら